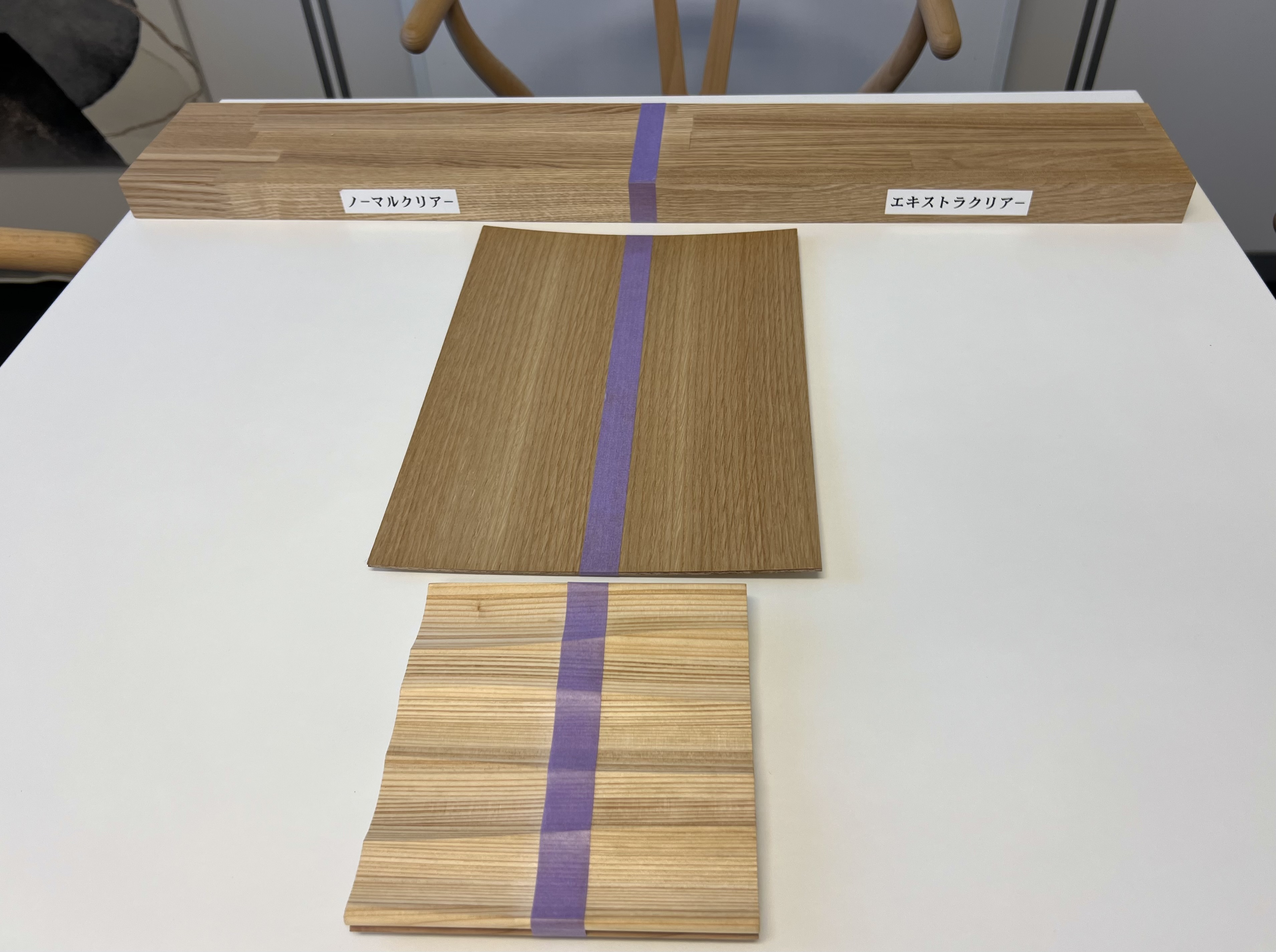「和地たなか歯科様」、ついに建築が完成しました!
完成写真や設計のポイントについては追ってご紹介予定ですが、その前に少し様子を...
Instagramより▼

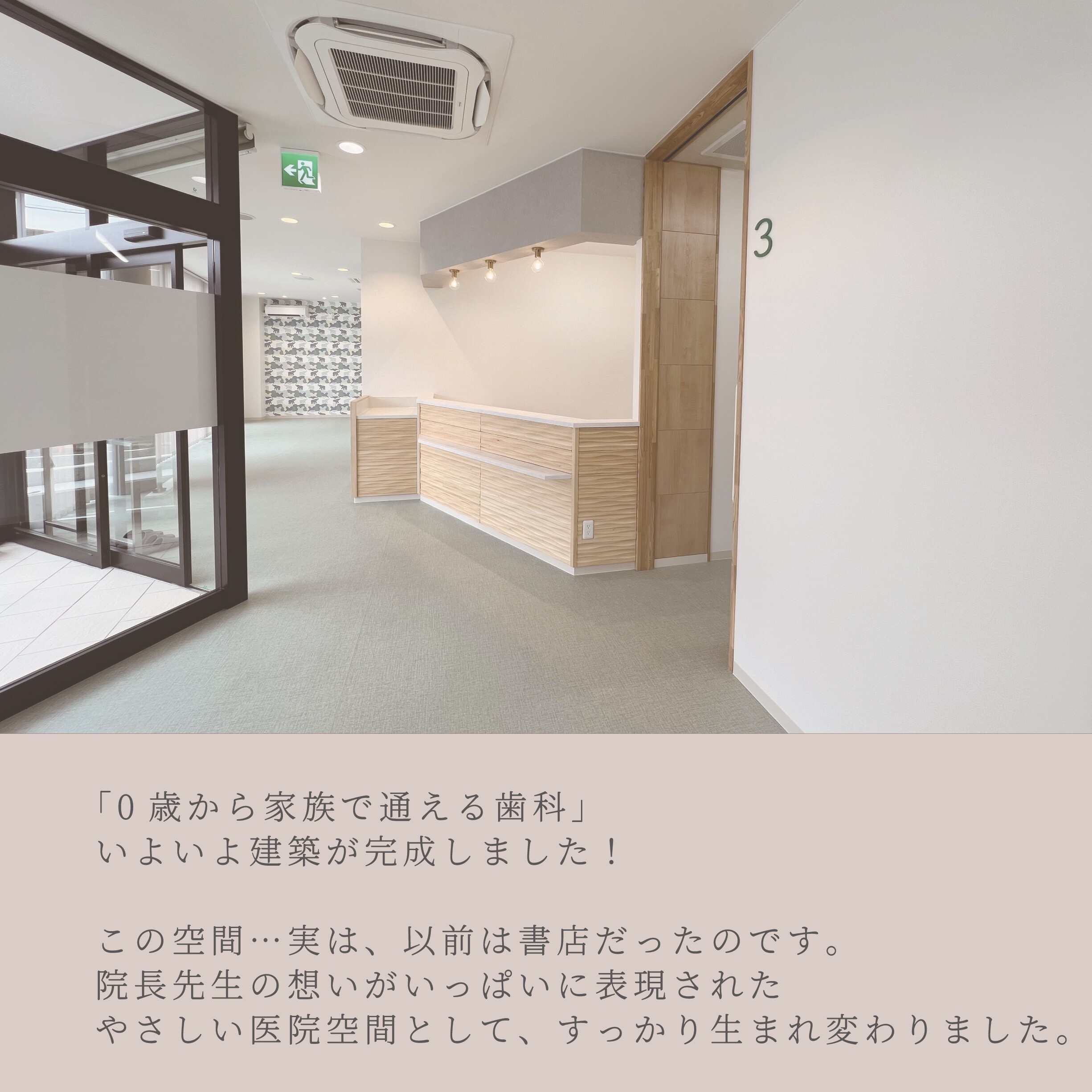
---
【内覧会のお知らせ】
開院にさきがけ、内覧会が開催されます。
5月24日(土)•25日(日)
場所:和地たなか歯科様
浜松市中央区和地町4757-1
・見学自由
・予約制の「体験会」
※詳細は、和地たなか歯科様の Instagram をご確認くださいね。
---
さて。前回のブログ以降に施工された内容です:
■外部
出入口へのスロープや階段を設置。ベビーカーや車いすのまま出入口までアクセスできるバリアフリー仕様です。
また、周辺には樹木も植樹。自然豊かな周辺環境に馴染みつつ、少し新しさをプラスする外観に仕上がりました。
■内部
床・壁・天井の内装仕上を行いました。
クリニックのテーマカラーである緑を基調に、明るく優しい素材でまとめています。
内装が終わったら...
造作家具の施工▼
照明取付▼
サイン(室内表示)の取付▼

待合ソファの設置▼
などを経て、
施工者検査(建設会社:浜建さんの社内検査)
↓
監理者検査(私達WARAKUSHAの検査)
↓
お施主様検査
を合格後、お引渡しとなりました。
いよいよ開院へ。
これから、建築空間もさらに素敵にのびのびと育っていきそうで、私たちもとても嬉しく楽しみです。
完成、おめでとうございます!
※今回の関連記事
↓
和地たなか歯科様工事:以前のブログ
(工事開始まで遡って辿れます)























 床の高さを上げる工事が始まりました。
床の高さを上げる工事が始まりました。